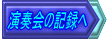METROPOLITAN MANDOLIN ORCHESTRA
第15回演奏会
この演奏会の補足情報は「マンドリン・オーケストラの周辺で」2004年8月9日以降のブログを参照ください。
1.日時
2004年9月11日(土) 18:00会場 18:30開演
2.場所
3.指揮者
4.曲目
○セザール・フランク(笹崎譲編曲)/交響詩「プシュケ」より第4曲「プシュケとエロス」
○モーリス・ラヴェル(笹崎譲編曲)/高雅にして感傷的な円舞曲(1911-12)
○セルゲイ・ラフマニノフ(笹崎譲編曲)/交響的舞曲 作品45(1940)
5.楽曲解説
セザール・フランク(1822~1890)
交響詩「プシュケ」より第4曲「プシュケとエロス」(1886~1888)
フランクは独創的な和声感や感性の流麗さにより近代フランスにおける重要な作曲家ですが、その作品は堅固な構成をもっておりドイツ的側面もあります。気品と豊かな叙情をもった旋律が、大きな弧を画くように上昇と下降をします。
交響詩「プシュケ」はギリシャ神話に基づく作品で、全6曲からなり後半には合唱も加わる大作です。美しい人間の娘プシュケに嫉妬した美の女神アフロディーテ(ヴィーナス)は、息子愛の神エロス(キューピット)に下賎でつまらない男に恋させるよう命じます。しかし、プシュケの美しい寝顔に見とれて、エロスは慌てて恋の矢で自分自身を傷つけてしまいます。そして、様々な試練の後にプシュケは神の仲間入りをし、改めて二人は夫婦になるのです。フランクの特徴的なオルガンのような響きと、ワーグナー風の官能性にあふれた作品です。
モーリス・ラヴェル(1875~1937)
高雅にして感傷的な円舞曲(1911~1912)
ストラヴィンスキーが、ラヴェルのことを「スイスの時計職人」と評したことはたいへん有名です。これはラヴェルの父親がスイス出身であることも関係するようですが、彼がたいへん精密と呼ぶべき音楽を書いたことによります。心地よく耳に響く音楽ですが、一方で計算し尽くされていることによる不気味さすら感じられるのです。
「高雅にして感傷的なワルツ」は彼の多くの管弦楽作品同様に、最初はピアノ曲として発表されました。初演は1911年、フォーレの弟子たちを中心とする独立音楽協会が主催する匿名演奏会でした。この時「高雅にして感傷的なワルツ」の作曲者を当てたものはごくわずかだったそうです。その後バレエ団からの依頼でオーケストレーションされバレエ音楽「アデライド、あるいは花言葉」として生まれ変わります。バレエの内容は、花に託した愛の表現をテーマとしたものだったようです。1912年パリのシャトレ座、ラヴェル指揮ラムルー管弦楽団によって、初演されました。実はシューベルトのピアノ曲に「34の感傷的なワルツ」作品50や「12の高雅なワルツ」作品77という作品があり、ラヴェル自身もこれらの作品を意識して作曲したことを認めています。対照的な性格を持つ7つのワルツと、これらの回想を含むフィナーレ・第8ワルツからなり、全曲、中断されること無く演奏されます。
セルゲイ・ラフマニノフ(1873~1943)
交響的舞曲(1940)
1917年、ロシア革命のためラフマニノフは家族とともにパリへ亡命、翌年アメリカへ渡ります。そこで、生活のために演奏活動に注力することとなります。大ピアニストとして名声を博したせいもあり、ピアノ作品の作曲家とした印象が強いですが、様々なジャンルの作品を残しています。作曲家としての活躍は主に20世紀に入ってからですが、同時代の作曲家たちがロマン派の音楽語法から脱却して新しい語法を探求していたことに対し、最後まで19世紀のロマン的情感を歌い続けました。
彼の最後の作品となった「交響的舞曲」は、外見的には似ていませんが本質的に同一のもので繋がっている3部からなる作品で、実質的には交響曲といってよい作品です。当初の原案では各楽章に「朝」「正午」「晩」、その後、「昼」「たそがれ」「真夜中」と名づけたようですが、最終的には表題が削除されています。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
第1楽章 ノン・アレグロ
ソナタ形式の要素を併せ持つ、序奏付の3部形式。烈しい、機械的なリズムで貫かれた主部は、大きなエネルギーを感じさせます。中間部では一転、風に乗って遠くへ流れていくような、牧歌的な歌となります。主題が再現し展開部風に扱われた後、自作の交響曲第1番の主要主題が変形して表れ、過去を回想するように静かに楽章を終わります。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
第2楽章 アンダンテ・コン・モト
ファンファーレに導かれる、不安げな序奏に始まります。主部は暗く幻想的な雰囲気をもった3つのワルツにより、構成されています。音楽は変化にとみ、テンポも自在に変化する個性的な楽章です。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
第3楽章 レント・アッサイ‐アレグロ・ヴィヴァーチェ
自由な形式のフィナーレ。スケルツォ風のダイナミックな主題が、変奏風に扱われ発展していきます。中間部では憂鬱で叙情的な旋律をゆっくりと歌い、甘美な様相を帯びてくると、再び、アレグロ・ヴィヴァーチェに移ります。後半では、グレゴリア聖歌「怒りの日」を挿入してクライマックスを築きます。ラフマニノフは、自作「死の島」「パガニーニ主題による狂詩曲」などにも「怒りの日」を引用しており、彼にとって重要な主題です。さながら死の舞踏を印象付ける場面ですが、ロシア正教の聖歌「アレルヤ」を加えることによって、死への恐怖の克服と神への崇敬を表すのです。ラフマニノフはこの曲の草稿の末尾に“私は神に感謝する”と書きました。それはこれが最後の作品であることを予感し、それを満足に完成させられたことを感謝することばだと言われています。
ユージン・オーマンディとフィラディルファイア管弦楽団により初演され、同団体に献呈されました。